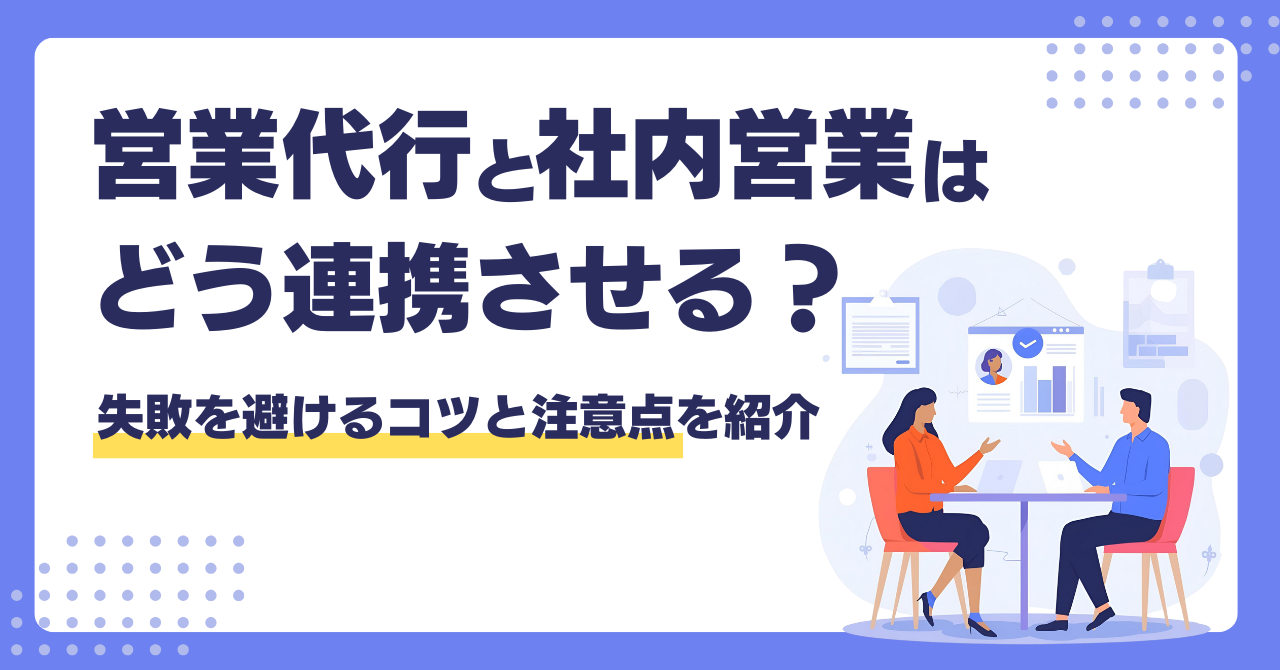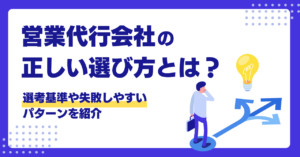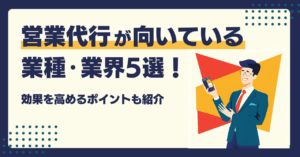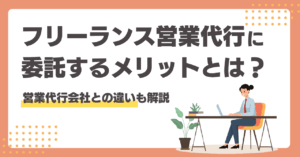連携とは「互いに連絡を取り協力して物事にあたること」を意味します。
営業代行と社内営業を連携させる目的は、自社の営業成果を高めるためです。お互いに連絡を取り協力して営業活動を推進できれば、営業部門の利益拡大を目指せます。
しかし、はじめて営業代行を検討する場合、「社内営業とうまく連携できなかったらどうしよう」と不安を抱えるかもしれません。
本記事では、営業代行の導入を検討している中小企業の担当者様に向けて、営業代行と社内営業を連携させるコツを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
営業代行と営業派遣の違い
営業代行とは、自社の営業活動の一部を代行会社が請け負うサービスです。営業代行会社には、営業スキルや経験豊富なプロフェッショナルが在籍しており、自社に代わって質の高い営業活動を実施してくれます。
営業派遣とは、派遣契約に基づき、派遣会社のスタッフが自社に派遣されて営業活動に従事するサービスです。営業経験のある派遣会社のスタッフが自社の現場に従事します。
両者の大きな違いは、指揮命令権の所在です。営業代行の指揮命令権は、営業代行会社にあります。たとえ、自社の営業部門責任者であっても、営業代行のスタッフに直接命令を下すことはできません。
一方の営業派遣の指揮命令権は自社にあります。自社の営業部門責任者が派遣スタッフに業務指示を出すことが可能です。
| 営業代行 | 営業派遣 | |
|---|---|---|
| 指揮命令権 | 営業代行会社 | 自社 |
| 契約方式 | 業務委託契約 | 派遣契約 |
| スタッフの特徴 | 営業スキル・経験を持つスタッフが所属しているケースが多い | 営業スキルを持つ人材、営業をやりたいと志願した人材が中心 |
営業代行と営業派遣を混同すると、営業代行と正しく連携を図れなくなります。両者の違いを把握しておきましょう。
営業代行と社内営業の連携に失敗する典型的なパターン
営業代行と社内営業の連携が失敗する典型的なパターンは、営業代行との情報共有がうまくいかないケースです。
失敗パターンは以下のとおりです。
- 重要意思決定権のない人物にアプローチしてしまった
- 商材に関する質問に不正確な回答をしてしまった
- 顧客に不信感をあたえてしまった
顧客や商材に関する情報共有が不十分だと、自社ブランドに傷がつくおそれがあります。
また、営業代行からの情報提供が不十分だと、顧客の現在のニーズや経営課題を把握することが困難です。効果的な営業戦略を立案できないかもしれません。
他にも、「役割分担が曖昧で業務の線引きが難しい」「営業代行のトンマナが自社の雰囲気に合わない」といったミスマッチも典型的な失敗パターンです。
こうした失敗を事前に防ぐためにも、営業代行と社内営業を連携させる必要があるのです。
営業代行と社内営業を連携させるコツ
どのような取り組みを実践すれば、営業代行と社内営業は連携できるのでしょうか。以下に、営業代行と社内営業を連携させるコツを紹介します。
情報共有できる仕組みを作る
営業代行と社内営業を連携させるためには、両者の間に情報共有できる仕組みを構築しなくてはいけません。
情報共有を行うことで、営業活動の内容がブラッシュアップされていきます。
自社から営業代行に提供したい情報は、次のとおりです。
- ターゲットの詳細(決裁権を持つキーマンは誰か、キーマンの詳しい情報)
- 商材の情報(概要、実績、メリットなど)
- ターゲットにふさわしい営業のやり方
反対に、営業代行から以下の情報を共有してもらえば、効果的な営業戦略を作成できるでしょう。
- 現在の顧客が抱えている課題ニーズ
- 現場レベルでの予算感
- 他のサービスの検討状況など
営業代行と情報共有を図る方法として、CRMやSFAといった「営業活動支援ツール」の活用が挙げられます。小規模なプロジェクトの場合は、ChatWorkやSlackなどのオンラインチャットツールを活用するとよいでしょう。
営業代行からのフィードバックを重視する
フィードバックとは、実際の仕事に対する評価や改善策を相手に伝えること。より良い成果を出すために行われるコミュニケーション手法です。
営業代行からのフィードバックには、営業代行のスタッフが現場で取得した顧客からの意見・感想が含まれています。商品・サービスの改善にいかせる貴重な情報です。
さらに、こうした意見・感想を営業活動に反映させると、「こちらの意見を大切にしてくれている」と、ターゲットから好感を得られるでしょう。
営業代行からのフィードバックは重要です。営業活動の現状や顧客の「今の」ニーズを確認して、営業活動を改善していきましょう。
お互いの役割を決める
営業代行と社内営業の役割分担を明確にすることで、営業の生産性を高められます。
たとえば、営業代行に新規開拓を依頼して、自社はリードの育成や商談の実現に専念する。営業代行にアポ獲得から商談化まで依頼して、自社は商談の成立に専念するといったような分業体制を築けるからです。
代表的な営業代行の種類と主な業務範囲は下表のとおりです。
| 種類 | 主な代行範囲 | 主な成果 |
|---|---|---|
| テレアポ代行 | 架電からアポイント獲得まで | アポイントまたは商談の獲得 |
| 手紙営業代行 | 企画、営業手紙の作成・送付、顧客のリアクションの確認まで | |
| 営業DM発送代行 | 営業DMの印刷から発送まで | |
| 問い合わせフォーム営業代行 | 営業メッセージの作成から送信まで | |
| インサイドセールス代行 | 新規開拓から商談の成立まで | 受注支援 |
| フィールドセールス代行 | 訪問営業から商談の成立まで | 新規開拓・既存顧客の関係構築・商談の獲得など |
| 商談代行 | 商談の準備から契約成立まで | 契約締結 |
※代行会社によってターゲットリストの作成も依頼可能
営業代行の種類と業務範囲を参考にして、自社の業務との境界線を明確にしましょう。
成果を確かめるための基準(指標)を設ける
営業代行の成果を確認するためには、客観的な基準が必要です。
ここでは、CPA(Cost Per Acquisition)を利用して成果を確認する方法を紹介します。
CPA(Cost Per Acquisition)とは、顧客1人あたりの獲得にかかった費用を意味する「顧客獲得単価」です。以下の計算式で求められます。
CPA=営業代行にかかったコスト÷顧客獲得件数
テレアポ代行を例に挙げてみましょう。
<テレアポ代行の費用感>
- 初期費用:0円
- 1コール単価:400円
- 成果報酬(アポ獲得):1件あたり10,000円
- 月間コール数:1,000件
- アポイント獲得数:40件
- 商談化率:50%(20件)
- 受注率:25%(5件)
上記の場合のCPAは、
営業代行にかかったコスト=初期費用0円+(400×1000)+(10000×40)=80万円
CPA=80万円÷5件=16万円
受注1件あたりの費用が16万円となります。
CPA(Cost Per Acquisition)を用いて、営業代行の成果を客観的に確認しましょう。
営業代行と社内営業を連携させるための3ステップ
営業代行と良いビジネスパートナーとなるための手順を紹介します。
1.自社の営業課題を明確にする
営業課題を明確にすることで、自社が補強すべきポイント(弱点)に対して適切な営業代行を導入できるようになります。
たとえば、「新商品をリリースすることになったが、営業スタッフのスキルが不足していて、営業成果が上がらない」という場合、商品を認知させるための営業リソースが必要となります。
そこで、営業代行を利用すると、営業スキルの高い人材に自社の営業を任せられるのです。自社で営業スタッフを採用・育成することなく、さらにスキル不足という課題を解消しながら営業の業績アップを目指せます。
営業部門で補強すべきポイントは、企業によって多種多様でしょう。まずは、今の営業部門の現状を見つめ直し、真っ先に解決したい営業課題をピックアップしましょう。
2.営業代行に求める成果を決める
営業代行と社内営業を連携させるためには、営業代行に求める成果を決めなくてはいけません。
営業代行に求める成果を決めることで、営業代行の費用対効果を評価できるようになるからです。
営業代行を導入する前に、具体的な成果を定めましょう。
3.代行選びに時間をかける
営業代行の費用は安い投資ではありません。自社の営業を成功させるために、代行選びには十分な時間をかけるべきです。
地域の営業代行を探したりインターネット検索を利用したりして、じっくりと探してみてください。
おすすめの方法は、「営業代行比較サイト」の利用です。
営業代行比較サイトには、複数の営業代行会社が登録されています。自社に合った営業代行を効率的に探せるのです。さらに、営業代行の概要や特徴も確認できます。社内営業と連携しやすそうな営業代行を効率的に見つけられるでしょう。
営業代行を絞り込んだ後も、相手と良いビジネスパートナーになれそうか契約を交わす前にじっくりと検討することをおすすめします。
営業代行に依頼するときの注意点と対応策
営業代行に依頼するときの注意点と対応策を紹介します。
情報共有とセキュリティ
営業代行とは、自社と顧客の情報を共有することになります。万が一、情報漏洩が起きると自社の責任問題に発展するかもしれません。セキュリティ対策のしっかりしている営業代行を選びましょう。
具体的なポイントは次のとおりです。
- 情報漏洩に対する意識
- 情報漏洩を防ぐ技術的な対策を実施しているか
- 社内への啓蒙活動などを行っているか
「USBや外付けSSDなどの外部記憶媒体の使用を制限」「社内でセキュリティに関する研修を実施」「情報漏洩を防ぐためのマニュアルを整備」など、具体的な対策を実施している営業代行をおすすめします。
悪質な代行業者と回避方法
悪質な代行業者とは、以下の項目に該当する営業代行です。
- 実態のない実績をアピールする
- 顧客の意向を無視した強引なアプローチを実行する
- 進捗状況の報告が全くない。訊いても返事がない
こうした悪質な営業代行を回避するポイントは、次のとおりです。
- 営業代行の運営年数や実績におかしな点がないか確認する
- 第三者の評価(営業代行を利用した企業)の評判・レビューを確認する
- 代行選びの際に担当者と直接コミュニケーションの機会を持つ
上記以外に、「候補となる営業代行を2~3社に絞り込み、複数の代行会社を比較検討する」方法も有効です。
営業代行の選び方を詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
参考記事:営業代行会社の正しい選び方とは?選考基準や失敗しやすいパターンを紹介
予測が難しいトラブルと対処法
営業代行を利用すると、予測が難しいトラブルに出会うケースもあります。
たとえば、営業代行のアプローチに対して、顧客が「しつこい」「強引だ」とクレームをつけるケースです。たとえ、営業代行としっかり情報を共有し営業フローを確認しても、上記のようなトラブルは起こりえます。
こうしたケースでは、営業代行と連携を取った素早いフォローが大切です。事実を正しく確認して、ターゲットにいち早く連絡を入れましょう。そうすることで、顧客に誠実な態度を示し、マイナスイメージを最小限に抑えられます。
そのためには、コミュニケーションを重視する営業代行が必要です。連携体制を構築することに積極的な営業代行を導入しましょう。
まとめ
営業代行と社内営業の連携を成功させるコツを紹介しました。
営業代行と社内営業の連携を成功させる4つのコツは以下のとおりです。
- 情報共有できる仕組みを作る
- 営業代行からのフィードバックを重視する
- お互いの役割を決める
- 成果を確かめる基準(指標)を設ける
営業代行を導入し効果的な協力体制を築ければ、自社の営業活動を大幅に効率化できるはずです。
ぜひこの機会に営業代行と社内営業を効果的に連携させて、スムーズな企業成長を達成してください。